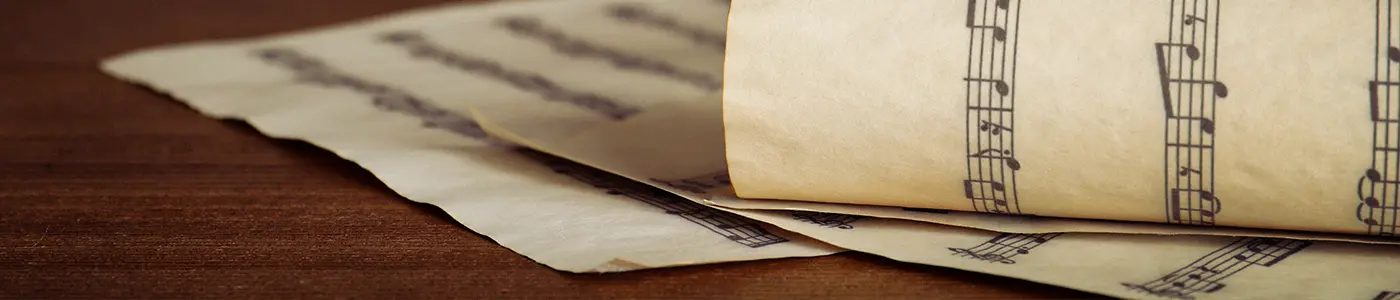10月10日、五反田文化センターにて開催された《さすらいと記憶 ─ 幻想曲のかたち》は、多くのお客様をお迎えし、おかげさまで無事終演いたしました。
ご来場いただいた皆さま、そして応援してくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。
本公演では、ピアニスト鶴澤奏が、16世紀ルネサンスのミランからシューベルト、ブラームスまで、時代を越えた“幻想曲”という形式を軸に選曲を構成し、記憶と感情の奥深くに触れるようなひとときをお届けしました。
その中心に据えた《さすらい人幻想曲》では、理性と激情のあいだを繊細に往復する表現が高く評価され、終演後には「圧倒された」「言葉を失った」「こんな集中で聴いたのは久しぶり」といった声が数多く寄せられました。
みのりの眼ならではの視点と、鶴澤奏さんの誠実で濃密な音楽が交わることで、幻想曲という“かたち”に込められた、時代を越えた感情のさすらいをお伝えできたのではないかと感じています。
ご来場くださったお客様の“生の声”を、許可をいただいたうえで以下にご紹介しております。
ぜひご覧ください。
今回の鶴澤さんはメインにシューベルトのさすらい人幻想曲を据えて「さすらい」と「記憶」をキーワードに美しいファンタジーの世界を描き出しました。
なんと言っても今回のコンサートを深みのあるものにしていたのは一曲目のルイス・デ・ミランの作品があってこそでしょう。
本来がビウエラのために書かれているのでそれに近いギターで演奏されることはありますがまずピアノでは普通弾かれない作曲家。
しかしメランコリックでシンプルなメロディはピアノによく合っていて惹かれます。
ビウエラやギターは持ち運びしやすいので旅というコンセプトにもぴったり。
旅立つ兄を見送るバッハ、追憶のブラームスもまた深い味わいの前半を終えて後半はこちらも友人の旅立ちに寄せたシューベルトのアレグレット。
後期のピアノソナタにも通ずる光と闇が交錯する儚げな音楽ですが鬼気迫る鶴澤さんの演奏に胸を突かれます。
スコットランド出身のアレクサンダー・マッケンジーの作品はどこか懐かしいメロディと色彩的な和声がいかにも幻想的で次のメンデルスゾーンのスコットランドソナタの嵐の吹き荒れるような緊張感とは対照的。
このメンデルスゾーンが格調高い名演だったのでここで終えたとしても満足度高い内容ですが、第3部ともいうべきシューベルトのさすらい人があることでより統一感のある印象になりました。
シューベルトの音楽はそれ自体が旅するようなもので何か目的があるというより自由気ままなように聴こえてまさに「さすらい人」。
ベートーヴェン風ですがたぶんベートーヴェンを弾くように演奏すると的外れになるところをおおらかな歌で編み上げた鶴澤さんの見事なシューベルトでした。
アンコールはシューマンの3つのロマンスより第2曲。まさにシューマンも夢に遊ぶ幻想の人でその憂愁の世界に引き込まれました。