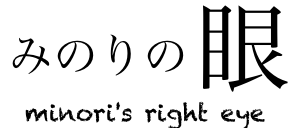トマシュ・リッテルという名前よりも、きっと「川口成彦が2位だったショパンコンクールで1位をとったピアニスト」という方が通りが良いでしょう。
現に私もそうでした。
アー写ではいかにも今風の「成功した」美男美女風に撮られてしまっているけれど、実際にステージに現れた彼は違う。
「やあやあ、みなさん、本日のスターが登場しましたよ!」とばかりに拍手クレクレと登場する芸人や芸能人のような奏者も多い中で、彼は完全にオーラを消して現れ、まるで機械の修理に来たエンジニアのような雰囲気で、客など存在しないかのように気負いなく自然に弾き始める。
リッテルの師でもあるリュビモフの、クルクルと動き回りパタリと眠る多動の子供のようなモーツァルトを知っていると、少し動きが緩慢で重い気もしてしまうけれど、それは解釈や技術の問題ではなく、奏者と作曲家の気質の違いのように思う。
リュビモフの資質がモーツァルトに合致しすぎていたからかとも。
ベートーヴェンもショパンも素晴らしい。
これは個人的な受け取り方に過ぎないけれども、ショパンをただ感傷的に甘ったるく甘美にだけ弾かれることも多い中、私にはショパンの曲とは、この世に閉じ込められて出られない絶望と諦観の音楽のように感じられていました。
この世はろくでもない牢獄でもあるけれど、だからこそ、諦めて美しい良い面に目を向けて前向きに強く生きなくては!という気にさせる奏者も稀にはいます。
でもリッテルの『24の前奏曲』はそれ以上でした。
突然ですが『トゥルーマン・ショー』という映画をご存知でしょうか。
主人公が虚構の世界に気付き、全力でそこからの脱出を試みるという物語。
リッテルの『24の前奏曲』からは、そんな気概が感じられて、おそらくショパン自身が初期設定した世界観からも先に進めてしまっているのではないかと。
諦めて安住するのではなく、立ち向かう音楽に、思わず落涙。
「私の解釈」「私の音楽」それを認められたいがために必死で努力し、そうなった暁が夢であり成功であるという人も多いでしょう。
個人が社会的な地位を得るための手段としての音楽、それはエゴの音楽でもあり、小さな小さなごく個人的な音楽です。
そういうものを聴いていると、逆に何かを奪われるようだといつも思います。
「私が輝きたい」「私がスポットライトを浴びたい」、そのための外部装置にさせられてしまうんです。
リッテルはまずは作曲家に、次に音楽に、そして音楽の背後にある大いなるものに。
それらのために全力を尽くした後に全てを明け渡し、良き霊感を待つ音楽でした。
持ち上げられたスターと、その持ち上げ要員としての観客、という役割を強要されていると感じることがままあります。
教祖がいて信者がいて、その依存関係のためにお金を介す宗教団体化してしまう。
でもこんな音楽の前では、そのようなくだらない既存の枠組みが崩壊してしまう。
個人崇拝ではなく、一人一人が自らの足で立ち、大いなるものに個人でつながることが可能になってしまうから。
そんな解放の音楽でした。
素晴らしい。
文責:前原麗子